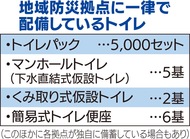相鉄いずみ野線緑園都市駅の改札付近で電車の接近を知らせ、駆け込み乗車を予防するサイン音の試験導入が3月1日から始まった。フェリス女学院大学の学生が実体験を基に発案し、相鉄グループとの協議・調査を経て、実現した。接近サイン音の導入は相鉄線で初。
「電車の音が聞こえた時、自分が乗りたい電車なのかわからず、とりあえずホームへ駆け上がるが、空振りに終わることが多い」――。そんな声から生まれたのが今回試験導入されたサイン音だ。聞いただけで接近している電車がどの方向へ向かうどの種類かが分かるよう、横浜方面への上りは音が上がり、下りは音が下がるメロディーになっている。快速は各停と比べ、音符の数が多くテンポも速い。演奏する楽器も上りと下りで分け、判別しやすいよう工夫されている。駆け込み乗車を予防したいという思いから、サイン音には音楽の速度記号で「歩くような速さで」を意味する「アンダンテ」という名が付けられた。試験導入に合わせ、駅改札などでポスターによる紹介を行っているほか、相鉄グループホームページでも試聴することができる。
このプロジェクトに取り組んだのは、フェリス女学院大学音楽学部音楽芸術学科「音環境デザインゼミ」に所属する4年生9人と講師の船場ひさおさん。同大音楽芸術学科では、身の回りの音環境で改善・提案したい事柄について考える授業を行っている。その際、緑園都市駅について取り上げる学生が毎年いたことから、2015年度は同駅の音環境の良い点・悪い点に焦点を当てた。そこで学生から上がったのが、接近する電車の種類が分かるサイン音の製作だったという。企画提案書とサンプル音を作成し、昨年2月に履修者有志が相鉄グループへ提案したところ、賛同が得られ、共同プロジェクトとして進めることが決まった。
始動するにあたり、授業履修者では対応が難しいことから、同様の課題をより専門的に研究している「音環境デザインゼミ」がプロジェクトを引き継ぐこととなった。合同定例会議に加え、学生や関係者を対象にしたアンケートを実施。夏に行った実地検証では、駅利用者がホームへ向かう時間を調査するため、ストップウォッチを片手に何度も構内を往復したという。講師の船場さんは「相鉄さんからは鉄道のプロとしてのご意見やアイデアをいただき、ゼミ生からは音楽の聞こえ方や音量といった相鉄さんが気付いていなかった事柄をお伝えできた」と振り返る。
相鉄グループ広報担当者によると、今後利用者からの評判が良ければ、全駅での導入検討の可能性があるという。
泉区版のトップニュース最新6件
|
|
|
|
|
|
|
|
|