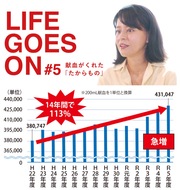倒木の恐れがあった諏訪神社(箕輪町3の8の9)境内の樹齢約300年になるケヤキが現在、地元NPO「樹木医協力会」や地域住民らが協力して行った大枝伐採や土壌改良によって徐々に元気を取り戻している。12月6日(土)には一般公開で木の「治療」を行う。
1730年代、江戸時代中期に植えられたと伝えられるこの大ケヤキに倒木の危機が訪れたのは昨秋。関東地方に暴風雨をもたらした台風の時だった。近隣住民から「木がグラグラして倒れそうで危ない」との声があった。
同神社の石川稔氏子会総代はそれを受け、ケヤキが市の名木古木(注)に指定されていたことから「何とか保存したい」との思いで市環境創造局に足を運んだ。そこで、日吉本町のNPO『自然への奉仕者・樹木医協力会』(安部鉄雄理事長)を紹介された。
大枝3本を伐採
最適な保存方法を検討した同会らは昨年12月、幹の音波検査を実施。その結果、面積の6割以上が空洞であることが分かった。今年に入り「ワイヤーを張って支える」「支柱を立てる」などの意見もでたが、倒木を避けるためには大枝の重量が負担となることから3本を切る必要があるという結論に達し、これを実施。3月には、木の空洞部分に植物を腐植化させた泥炭などを詰めた。また、土壌の通気や保水力などの改良を目的に土壌改良を実施し経過を見てきた。同会は「根本に材を腐らせるサルノコシカケが生えていました。また、敷地内の建物整備でこれまで2回の盛土があったようで、それが根に影響したのではないか」と衰退原因を分析。その後の4月から8月にかけて多くの新芽が確認できており「徐々にではあるが樹勢を取り戻してきている」と話す。また、石川総代も「少し不安もありましたが、ケヤキが何とか持ち直してきたことにホッとしている」と話した。
研究成果発表も
同会らは6日(土)、これまでに行った土壌改良の効果測定や今後の樹勢回復に向けた治療を一般公開で実施する(参加無料)。時間は午後1時から3時まで。ボランティアで参加している玉川大学農学部・山岡好夫准教授と学生らによる研究成果発表も行う予定だ。

|
港北区版のトップニュース最新6件
|
|
|
|
|
|
|
|
|