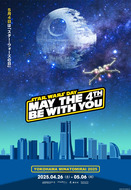敬老パスの利用状況を把握するため、横浜市は従来の紙製パスを廃止し、10月1日からプラスチック製の「ICカード」を導入した。変更直後には多少の混乱も見られたが、市では「利用実態のデータを収集し、持続可能な制度設計に役立てたい」としている。
高齢者の社会参加と福祉の増進を図るために、1974年に導入された「横浜市敬老特別乗車証(敬老パス)」。70歳以上の市民が所得などに応じて年間3200円〜2万500円を支払うことで、市内を運行するバスや市営地下鉄などが乗り放題になる。
制度開始当初は7万人だった交付者は、高齢化により年々増加。20年度末には40万7千人が交付を受けた。事業費も21年度は126億5700万円。市税負担額は105億4700万円に膨れ上がっている。
利用者が増加する中、横浜市では19年に、制度のあり方に関する検討専門分科会を設置。敬老パスを持続可能な制度としていくためには、利用した日時、回数、交通機関などの実績を正確に把握する必要があると示された。そこで市は21年度予算にIC化のためのシステム構築費を計上。22年10月からのICカード化に踏み切った。
利便性に不満の声も
導入されたICカードの敬老パスは、専用機器にカードを読み取らせる必要があり、地下鉄の自動改札は利用できない。市担当課によると、新たなパスで自動改札を通過しようとする人が後を絶たず、利用方法に関する問合せが相次いだという。また、読み取り機器の設置場所が一定ではなく、分かりづらいとの声も聞かれていた。
市は対応策としてシルバー人材センターに依頼した「案内役」を市内20駅に配置。読み取り機器の設置場所を11月1日からは全駅で、有人改札窓口に変更した。市担当課は「早く慣れていただくため、周知を徹底していきたい」と話している。
山中竹春市長は75歳以上の敬老パス無料化を公約に掲げており、今回のICカード化で得られる利用実績などを踏まえ、持続可能な地域の総合的な移動サービスについて検討を進める考えだ。
旭区・瀬谷区版のローカルニュース最新6件
|
|
|
|
|
|
|
|
|