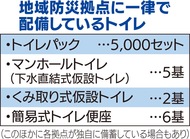あす9月1日は「防災の日」。今年は1923年の関東大震災から100年の節目となる。いつ起きるか分からないとされている大規模地震の備えとともに、台風やゲリラ豪雨なども多い季節を迎え、風水害への備えについて泉区役所の山口賢区長に話を聞いた。
――泉区の防災を考える上で、地域特性として留意しているポイントはありますか。
「泉区には和泉川、境川、阿久和川、宇田川と大きく4つの河川があります。河川の流域については一般的に地盤がゆるく、大規模地震の被害想定でも大きな揺れとなるリスクがあります。
河川については風水害の観点からも注意が必要で、例えば岡津地区は阿久和川に子易川と領家川が合流しており、ハザードマップでもリスクが確認できます」
――大規模地震のリスクとしてはどんな想定をしていますか。
「泉区には住宅密集地があり、特に中田地区としらゆり地区は大規模地震の際に大きな延焼火災が生じるリスクがあり、6件の火災から3000棟に延焼する試算もあります。道路の幅も狭いため、緊急車両が進入しにくいことも延焼拡大につながるとされています」
感震ブレーカーで火災発生を予防
――被害を最小限にするための対策は。
「まずは火災を発生させないことです。特に注意が必要なのが、停電から電気が復旧した時の通電火災です。大きな揺れを感知してブレーカーを自動的におとす『感震ブレーカー』などの機器が有効だと思います。
こういった対策を多くの人が知ることが地域の防災にもつながりますので、やはり啓発から一人一人の防災意識を高めるというのが重要な対策になるのではと思います」
――近年の泉区での防災の取り組みにはどんなものがありますか。
「昨年度は浸水ハザードマップを作り、全戸に配布しました。またあわせて制作した泉区震災対策パンフレット『もしもにそなえよう』では備蓄品のリストや緊急連絡先の記入欄もあり、実用的と好評をいただいています。現在追加で増刷準備を進めています。
また、大規模災害発生時には行政による『公助』には限界があり、『自助』『共助』の備えが欠かせません。その自助について、気軽に学べる動画を区役所では作成しており、今年度から公開しています(下記二次元コード参照)。
地震編、風水害編、備蓄編とありますので、ぜひお時間のある時にみなさんで観てみていただけたらと思います」
防災に強く住みよいまちを
――昨年度、領家中学校地域防災拠点では、より実践的な想定のもと、参加者300人を超える大規模な防災訓練を実施しました。防災訓練を充実させるためにはどんな工夫がありますか。
「今年は中田中学校地域防災拠点で10月に実施予定です。こういった大規模な訓練とともに、拠点立ち上げの基礎を確認する訓練も並行して実施してゆくとより効果的なのではと考えています。
また地域協議会での検討をもとに、今年度から各地区のご要望に応じ、防災に専門知識を有する防災アドバイザーの派遣を開始し、防災訓練を支援しています。
防災に関しては若い世代も関心が高く、これをきっかけに地域活動に関わってもらえたらと思います。やはり日頃からの顔の見える関係作りが、災害時の大きな力になると思います」

泉区震災対策パンフレット
|

|

震災対策動画の紹介ページ
|
泉区版のトップニュース最新6件
|
|
|
|
|
|
|
|
|