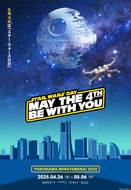常盤台地区連合町内会(石川源七会長)が今年度、創立50周年を迎えた。その歴史を語る中で外せないのが横浜国立大学との関係。学生団体が地域活性化に取り組むなど、近年特に連携を深める両者の歩みを振り返る。
1972年に当時の和田地区連合町内会から9自治会と1町内会が分離し発足した、常盤台地区連合町内会。その2年後には県内に分散していた横浜国立大学のキャンパスが常盤台に移転しはじめ、1979年に常盤台キャンパスが完成した。
当初は年に一度会議を行うくらいだった両者の関係が深まるきっかけとなったのは2005年。連合町内会の会長に山口和秀さん(現相談役)が就き、翌年には定例役員会に横浜国大が参加するように。
地域ケアプラザの開設に伴い2008年からは大原一興教授=人物風土記で紹介=の研究室が中心となり、学生と地域住民が街の課題を話し合う「まちづくりワークショップ」がスタート。これまでに50回以上実施され、住民主体の羽沢横浜国大駅周辺「バリアフリー基本構想」提案にも繋がった。
現在は地区社協と協働でキャンパスと地域をつなぐ「ときわだいマップ」を作成した「YUC」、学外農地で育てた野菜をコミュニティハウスで販売する「アグリッジプロジェクト」、地域の子どもたちの遊び場としてワゴン型の屋台を不定期出店する「ハマの屋台プロジェクト」など様々な学生団体が常盤台で活動。「地域の新しい文化」と呼ばれるまでになっている。

学生と地域住民のワークショップ
|
|
|
<PR>
保土ケ谷区版のローカルニュース最新6件
|
|
|
|
|
|
|
|
|