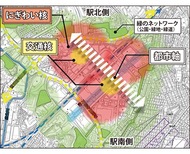今春に開館10周年を迎え、累計来館者数が8万人を突破した明治大学平和教育登戸研究所資料館(山田朗館長=人物風土記で紹介)。終戦75年をあす8月15日に控え、山田館長は「登戸研究所は特殊な場所。掘り下げると戦争全体の本質につながる話がいくつかある。そこを広げていきたい」と展望を示す。戦争の記憶を継承しようと、試行錯誤は続く。
旧日本軍の研究施設を利用した博物館として、2010年3月29日に開館した登戸研究所資料館。同館では年1回、さまざまな研究テーマで企画展を続けてきた。昨年11月からは「少女が残した登戸研究所の記憶」を開催していたが、コロナ禍による臨時休館で3月に休止。現時点で開館と企画展再開のめどは立っていない。第10回にあたる同展に秘められたエピソードは、今から約80年前にさかのぼる。
現在の明治大学生田キャンパスの場所にあった「陸軍科学研究所登戸実験場」は1939年、「登戸出張所」と名称を変更。これは、従来の電波兵器研究部門を第一科とし、毒物や生物兵器を開発する第二科と中国の偽札などを製造する第三科が新たに加わり、総合的な秘密戦研究所として登戸研究所が確立したことを表している。
同館によると、この特殊な研究機関に関する物的資料は1945年の敗戦時に全て処分され、登戸研究所の活動を示すものは消失したとされていた。しかし、登戸研究所に勤務し当時10代だった関コトさんが、数百枚の文書「雑書綴」を所持していると89(平成元)年に名乗り出たのだった。企画展では、この文書から登戸研究所の秘密に迫ろうと試みている。
高校生らが開拓
同大文学部教授の山田館長は「この平成元年は、これまで口を固く閉ざしていた研究所関係者が語り始め、資料館開館にもつながった。大きな節目」と強調する。当時、研究所に関する記憶を継承しようと、法政大学第二高校の渡辺賢二教諭と同校生徒らが当事者へのインタビューを敢行。元所員で所長の右腕と言われた伴繁雄さん(93年没)の証言を得ることができ、後に本人の手記『陸軍登戸研究所の真実』刊行にも至った。
伴さんの息子や孫も、資料館に協力を寄せる。「関係者のこうした気持ちがなければ研究を進めることは困難」と山田館長。「戦争の責任は重大だが、なぜ起きたのか、事実が何だったのかを後世に引き継ぐことが大切」と語気を強める。
同館は休館中もSNSで情報を発信。動画配信を活用した企画展の計画も進めている。
多摩区・麻生区版のトップニュース最新6件
|
|
|
|
|
|
|
|
|