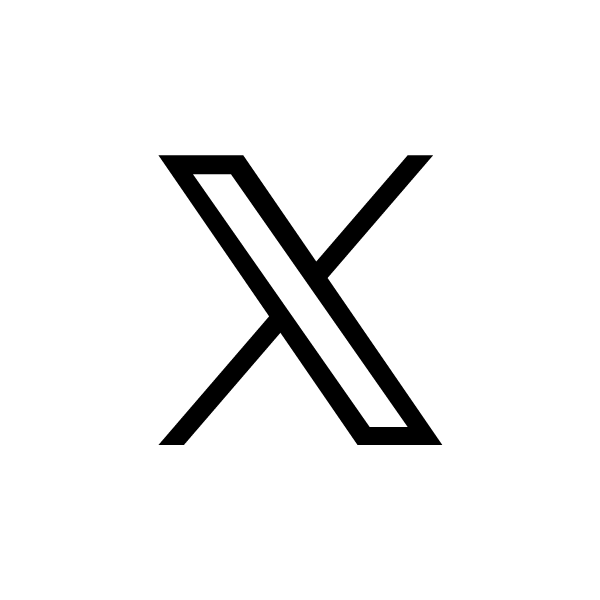2月6日、トルコ南部でマグニチュード7・8を記録する大地震が発生し、トルコとシリアであわせて5万6千人以上が亡くなった。日本医科大学武蔵小杉病院救命救急センターのセンター長を務める井上潤一さん(58)は、JICA(国際協力機構)国際緊急援助隊の医療チームの副団長として発災後1週間ほどの13日に現地入り。被災者らの医療活動にあたった。
井上さんは、救急医療や災害医療に従事する中で、1995年に国際緊急援助隊の隊員として登録。2003年のアルジェリア地震や04年のスマトラ沖地震の津波などで各国に派遣され、現地で医療支援を行ってきた。日本時間の6日午後にトルコ政府から支援要請が入り、同日夜、捜索・救助を行う救助チームが第一陣として現地へ出発。医療チームは10日に1次隊の派遣が決まり、井上さんは医師や看護師、放射線技師など75人を束ねる副団長として12日に出国した。
日常診療をサポート
イスタンブールから約850キロ、震源域に接するガズィアンテプ県オウゼリ市に13日に到着。被災した国立病院の医療機能を代替支援するため、同院が臨時診療所として間借りする職業訓練校の敷地内に、大小あわせて20張ほどのテントを設置した。日中に外来診療のみを行っていたこれまでの派遣とは異なり、初の試みとして24時間診療で入院や手術、分娩にも対応する「野外病院」を展開。「発災から1週間が経ち、地震による直接の負傷者や重症患者の対応はほぼ終わっていた。日常の診療のサポートが我々の役割」と井上さん。持病がある人やインフルエンザ患者、復興のための片づけでの事故の負傷者、粉じんによる喘息など、さまざまな症状で外来には2千人ほどが訪れ、手術は49件、入院は17件対応。リハビリのニーズも高く、柔道整復師の隊員によるマッサージも喜ばれた。
生活は過酷な環境
支援活動は「被災地に負担をかけない」ことが原則。発電機や浄水・供給システムを持ち込み、活動電力はすべて自家発電したほか、川の水や生活排水をろ過して再利用するなど自給自足で賄った。ホテルも営業していたが、余震で被災する可能性もあり、近隣の全天候型のサッカー場にテントを張り、キャンプサイトとして寝泊りした。寒暖差が大きく夜間にはマイナス5度ほどまで冷え込む過酷な環境。慣れない生活で体力が削られ、亡くなる患者にも接する中で「隊員にかかるストレスは大きい。つい頑張りすぎてしまう環境でもあるので、強制的にでも休ませることが必要だった」と井上さんは振り返る。最終的には構造の専門家のお墨付きを得たホテルに、順番に泊まることができたという。
温かい交流も
心に残るのは、現地の人々とのふれあいだ。トルコは1890年、軍艦「エルトゥールル号」が和歌山県串本町の沖合で遭難し、町民が献身的に救難活動を行って以来、日本との友好関係が続いている。片言の日本語で「こんにちは」と話しかけてくる子どもたちと一緒にボールで遊んだり、スタッフが折り鶴を作って喜ばれたりと交流を楽しんだ。日本語が話せる現地の通訳も多く、自らも被災しているにも関わらず献身的に対応してくれた。「いつも笑顔で接してくれた。現地の方の協力なしにはできなかった」。「ありがとう」と日本語で伝えてくれる人や、飛行機の機内放送では「救援に来てくれた人たちです」と紹介があり、一緒に写真を撮ってほしいと頼まれることもあった。
「東日本大震災の時に、世界の人たちが心を寄せてくれることで安心感があった。何百万人もの被災者から見たら支援できたのはごく一部だが、少しでも地域の人たちの力になれたならうれしい」と井上さん。今回の経験が、日本での災害時にも役立つ、とも力を込める。「地球の反対側の出来事だとしても、自分にも関係のあること。困ったときはお互い様、という気持ちがどんどん広がっていけば」

テントで野外病院を展開
|

協力した100人近くのメンバー
|
中原区版のローカルニュース最新6件
|
|
|
|
|
|
|
|
|