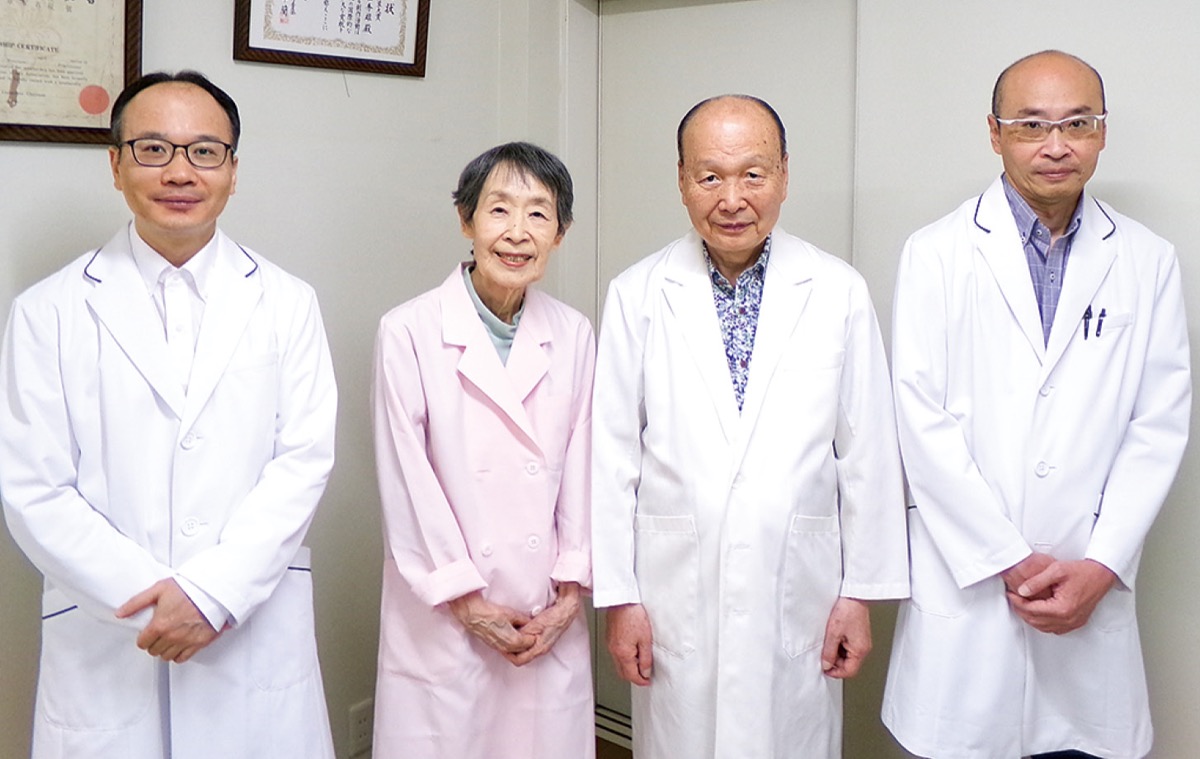中原区 トップニュース社会
公開日:2024.08.30
川崎市
5年前の教訓生かし対策
台風、内水氾濫へ「備え徹底」
8月16日に関東に接近した台風7号では、川崎市内で大きな被害は確認されなかった。甚大な被害をもたらした2019年10月の通称「令和元年東日本台風」からまもなく5年。市は対策を練り直し、「有事」に備えた態勢を整えてきた。
台風7号は強い勢力のまま本州接近が予測されたため、気象庁も早くから厳重警戒を呼び掛けていた。市では「東日本台風」の反省から新たに構築した「総合防災情報システム」を使い、全庁的に準備を進めたという。
この「システム」では、源流エリアも含めた多摩川の状況や、パトロール中の職員から寄せられる情報に加え、避難所の開設状況や避難所ごとの避難者数などの情報を集約し、全庁で共有できる。市民に対しても、必要な情報を速やかに発信できるという。
市が全庁的な防災態勢に入ったのは15日午後3時。「災害警戒本部」が設置され、避難所開設を伴う「3号動員」態勢に。通常は災害の危険度を示す「警戒レベル3」段階の態勢だが、前倒しの対応だった。担当者は「明るいうちに避難していただけるようにとの判断だった」。5年前は市民への情報発信が手薄だったが、今回はSNSやメールに加え、地域の自主防災組織に配備した受信機に向け、こまめに情報を発信したという。
午後6時30分には市内計177カ所で避難所を開設し、「高齢者等避難」を発令。学校の場合は体育館の開放が通例だが、熱中症対策の観点から、冷房が使える教室を開放。最終的に全域で最大計83人が避難した。
市の担当者は「情報の取り方や庁内のやりとりなど、5年前の反省から改善された点は多い」と振り返る。一方、福田紀彦市長は26日の会見で「情報の流し方など十分ではなかった」と課題を口にした。
業者と合同訓練も
市が「東日本台風」で突き付けられた最大の課題は、街の排水能力がパンクした状態の「内水氾濫」への対策の不備だった。当時は市街地に降雨があったことから雨水を多摩川へ排出する「排水樋管ゲート」を開放し続けたため、水位が上昇した多摩川への雨水排出が難しくなるとともに川の水が市内へ逆流。市街地の浸水被害が発生した。
そのため市は「排水樋管」の運用を見直し、ゲートの開閉を完全に電動化。具体的には、事実上の「水路」である樋管内の水位や川の水位を測る観測機器を設置し、計器からの情報を集めながら開閉を行える「遠隔操作」へと変更した。
浸水時に街から川へ水を逃すための排水ポンプ車も4台導入。ポンプ車の力を最大限活用するため、排水ポンプ専用のマンホールを市内5カ所の「ゲート」付近に開設。通行止めにすることなく多摩川へとホースを渡せる「横断管」を多摩川沿線道路の下に通すなど、必要な土木工事を進め、協力事業者などによる合同訓練も重ねた。
16日は事前に調整のうえ、排水ポンプ車の稼働に対応する約70人が待機した。今回は実践には至らなかったが、担当者は「適切に対処できるよう最大限の備えをした。今後も気を引き締めて対応する」と話している。
ピックアップ
意見広告・議会報告
中原区 トップニュースの新着記事
コラム
求人特集
- LINE・メール版 タウンニュース読者限定
毎月計30名様に
Amazonギフトカード
プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや
お得な情報などを、LINEやメールで
無料でお届けします。
通知で見逃しも防げて便利です!