このシリーズコラムでは、相模原の司法の現状と課題について、市にゆかりのある弁護士が解説する。大谷豊氏が担当。
-・-・-・-・-・-
相模原地域司法制度懇話会は、相模原市の市民相談課の職員、2002年1月25日に開催された市民集会に賛同をいただいた大学の教授の先生方、相模原で活動をされている弁護士などが毎月会合に参加し協議を重ね市民集会から10カ月後に発足した組織です。
発足にあたって市民に理解できる活動をしていくという視点から、裁判所があることが市民生活とどのような関係にあるのか、裁判所支部とは何か、どういう機能があるのか。そして合議制とはなにか、という基礎的な用語の勉強会から始まりました。これは、相模原市の市民相談担当者が主導的な役割をしていたことからすれば当然のことでした。ところが、このことは協議に参加している法律専門家の学者や弁護士にとって驚きを隠せなかったようで、むしろ新鮮に映り、これらかの設立に向けて真剣に議論するようになったのです。
裁判所があるということは、その街は生き生きとして活気づいていると言われています。街に住む人たちが自分たちで問題や課題を解決し、それによって活性化していくということのようです。争いが始まっても近くに裁判所があれば、すぐに裁判所で解決ができ、いつまでも争いを引き継がないので、街全体が安定し発展していくということなのでしょう。
裁判所の支部とは何かについては、神奈川で言いますと、横浜にある裁判所が相模原にもあるということを意味しています。横浜の裁判所で行われていることが相模原の裁判所でも同じことができるということです。
支部とはかつては裁判所の機能が一部縮小されたものと機能が縮小されていないものとがありましたが、現在では、このような区別はなく、すべて同じに扱えるようになっているのです。機能として最も大きな特徴は裁判所で行われる事件の審理が合議で行っているか単独で行っているかということです。合議での審理、合議制というのは、3名の裁判官によって事件を審理・判決する制度。事件を合議で扱うかは、刑事事件では法律によって決まっていますが、民事事件では、そのような決まりはありません。事件が複雑で慎重を要する、医療過誤事件のように専門性を要する事件などが、裁判所の裁量によって合議事件として扱われるのです。
相模原の横浜地方裁判所相模原支部では、合議の審理・判決は行っていません。同懇話会は、相模原地域の住民の生活を守り、権利意識を向上させるための第一歩として裁判所での合議制の実現に向けての活動を開始したのです。
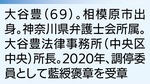
|
【物価高騰支援給付金】手続きは5月16日まで給付金の受取には支給要件確認書の返送が必要です。対象の方は期限までに手続きをお願いいたします。 https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026642/1030750/index.html |
<PR>
さがみはら中央区版のコラム最新6件
|
|
|
|
|
|
|
|
|













