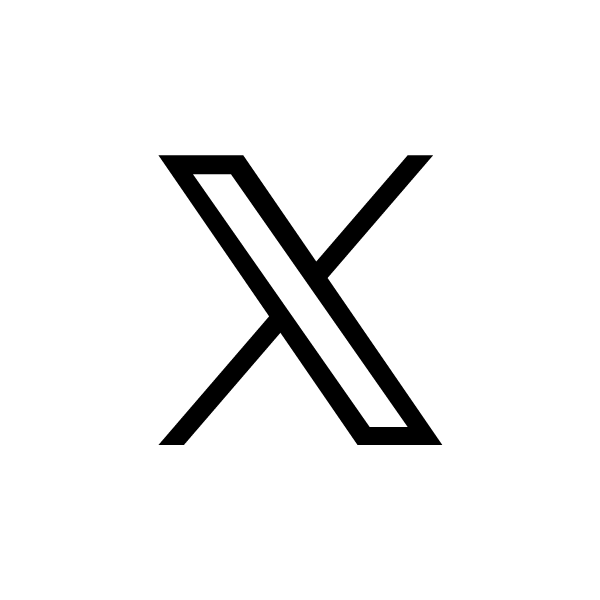終戦から74年となりました。戦中、戦後の苦難を絶対に忘れぬよう、激動の当時を生きた方々からお話をお聞きし、平和を心に刻む機会といたします。
「あの時、父と母はどんな思いで我が子を手放したのか。自分が子どもを持って初めて、親の気持ちを知ったように思います」。1944年、小学6年生の夏。親元を離れた集団疎開での暮らしは、今も鮮明に記憶に残る。
川崎市内に両親と5つ下の妹と暮らしていた北畠さん。働き盛りの男性が戦争に取られ、子どもは「少国民」と呼ばれ軍国教育が徹底された時代。学校の授業は消火リレーや手旗信号の訓練、手榴弾の投げ方など徐々に軍事色を増した。空襲が本格化する44年以降、工業地帯を抱え軍需生産で重要な役割を担っていた川崎は、米軍の最重点の攻撃目標の一つとして幾度も爆撃被害を受けた。灯火管制が敷かれ、サイレンが鳴れば防空壕に駆け込む日々。「酷い時は1日5回。食事どきや朝方、真夜中とか、精神的にダメージを受ける時間帯に集中していた」。機体の色がわかるほど低い位置で偵察機を見たこともあり、空襲後の焼け野原も目に焼き付く。「これで終わりかな」と命の危険を感じたこともしばしばだ。
やがて小学4年生以上の都市部の子どもたちを学校単位で避難させる集団疎開が始まり、親元を離れて伊勢原市の大山の民宿に移ることに。父が布団を背負い母が身の回り品を持ち、妹も一緒に民宿までついて来てくれたといい「最初は半分遠足気分だった」。同学年の女子20人で大部屋を使い、毎日リュックを背負ってふもとに下りて、日々の食糧を自分たちで調達する生活。月に一度、家族揃って来てくれる面会日を心待ちにした。
国鉄に勤め徴兵を免れていた父が、あるとき坊主頭になってやって来た。「戦争に行くのかもしれない」。怖くて聞けずにいたが、父の方から「どうだ、似合うか」と水を向けられた。男性は皆、丸刈りにすることになったのだ、と説明され「来月また来るよ」の言葉にホッとした。一方で軍服姿の父を見てみたい気もした。「国のために死ぬことは子ども心にも誇りだった。そういう教育だったのね」とぽつり。それでも、戦火が激しさを増すにつれ「また会えるかな」と不安を募らせながら見送った3人の後ろ姿は、今も忘れることができない。
家族離れて暮らすことを気に病んだ両親はその後、知人の紹介で相模原に居を構え、北畠さんの疎開生活も終りを告げた。ほどなく終戦を迎えたが戦後の食糧事情は厳しく、子どもたちは栄養失調に。戦中を生き抜いた父は48年、白血病で他界した。
過ちを繰り返さないためにも経験を伝えていき、正しい判断をしてほしい――。そんな思いで長年、小学校や公民館で自身の戦争体験を語ってきた北畠さん。「家族一緒に暮らせて不足なく食べられる、言いたいことを自由に言える毎日を当たり前と思わないで。世の中のことをきちんと知って、幸せな今だからこそ考えてほしい」
あっとほーむデスク
バックナンバー最新号:2024年11月24日号
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
お問い合わせ
- さがみはら中央区編集室
- 042-753-8500
- 042-769-7001
- 情報提供・ご意見はこちら
- 広告掲載はこちら
- 著作物の二次利用等はこちら
- 紙面の設置場所はこちら