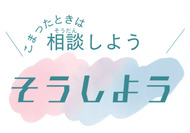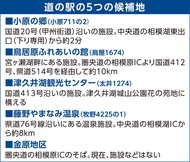東日本大震災が発生したわずか3か月後の6月11日、相模原市の友好都市である岩手県大船渡市に、炊き出しにあたる相模女子大学(文京)の学生の姿があった。さらに同年12月25日にも、多くの被災者が集まる避難所で、炊き出しを行った。
この時、中心となったのは同大学子ども教育学科の学生たちだった。そこで、大学としても継続的な復興支援活動を行っていくため、2012年8月、13人の学生有志により「被災地支援学生ボランティア委員会」を発足。大船渡市の仮設住宅を訪問し、心のケアを目的に住民と交流を持った。以降、定期的に大船渡市に足を運び、現地の人との交流会を継続。その数は19回に及んでいる。さらに大船渡市の水産会社・鎌田水産からサンマやホタテを直送してもらい、学生が炭火で焼いて販売する「ミニさんままつり」を学園祭の中で実施してきた。
15年度からは大船渡市の市花「椿」を活用した地域活性化事業「椿プロジェクト」も支援。同市内の保育園や幼稚園を学生が訪れ、椿学習を手伝ってきた。また神奈川県内での大船渡市支援イベントにも精力的に参加し、同市の特産品や委員会活動をPRしてきた。中学校から依頼され、復興の様子を伝える講師も務めるようになった。
2018年には「大船渡ビジネスプランコンテスト」の大学生部門で最優秀賞を獲得。地元企業と共同で『インスタ映え』する椿茶を活用したスイーツを開発・販売することで、大船渡市を「椿の里」としてさらに発展させるプランが高い評価を得た。
「復興支援学生ボランティア委員会」と名前を変えた同委員会の活動も10年目。炊き出しから始まり、心のケア、そして地域活性化へと形を変えて続いている。現在は21人が所属し、メディア情報学科3年の寺倉佳那さん(21)が委員長を務める。東日本大震災発生時、寺倉さんは小学5年生。「被災地のために自分にできることを考え、使っていない文房具などを募る活動をしていました」と話す寺倉さん。募金活動などにも従事したが、現地に行けないもどかしさも感じていた。だから相模女子大学に入学後、ボランティア委員会の存在を知り、すぐ籍を置くことを決めた。
しかし昨年から、新型コロナウイルス感染症の影響で集まれる機会が減った。大船渡市にも昨年2月を最後に足を運べていない。それでも、先輩が作った紙芝居『おおふなトンたんじょうものがたり』のデジタル化や、椿茶レシピの開発などに力を注いだ。交流のあった人々にも近況を伝える手紙と写真を送り、電話などでも連絡を取り合っている。「大船渡の人からも、『会いたい』という声をもらえる。10年活動を積み上げてくれた先輩のおかげです」と寺倉さん。「現地に行くと、私たちも元気をもらえる。今後も被災地の人の心に寄り添い、先輩たちの想いを受け継いだ活動を続けてほしい」と後輩にエールを送った。

大船渡市長を表敬訪問(2019)
|
湘南巻き爪矯正院 相模大野院無料相談会実施中!神奈川16店舗展開 施術実績41万回超 切らない・痛くない「負担の少ない施術」 |
【物価高騰支援給付金】手続きは5月16日まで給付金の受取には支給要件確認書の返送が必要です。対象の方は期限までに手続きをお願いいたします。 https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026642/1030750/index.html |
<PR>
さがみはら南区版のローカルニュース最新6件
|
|
|
|
|
|
ハンドメイド体験4月24日 |
|