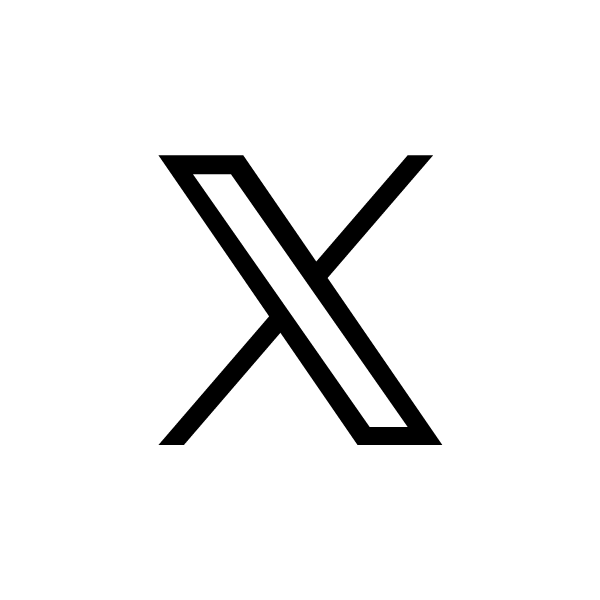1945年の第二次世界大戦終結から79年となる。その体験談は次世代へ伝えるべき貴重な教訓とされる。町田市内で暮らす3人の「あの頃」の記憶をたどってもらった。
神戸さん・広島で被爆
町田市内の被爆者の集まり「町友会」に所属し、広島の原爆投下地点から約4キロの場所にあった自宅で7歳の時に被爆した神戸美和子さん(86歳・市内在住)。
初めてB29を見たと記憶しているのは、投下の約3日前だった。それほど「広島は戦争末期でも穏やかだった」と話す。道を歩いていると、突然、知らない女性に腕をぐいっと掴まれた。「急いで、防空壕へ」。何が起きたかわからないまま、反射的に見上げた空に飛んでいたのは、白い飛行機雲を引き連れた大きな戦闘機だった。思わず「わあ、綺麗。勇ましい」と見惚れてしまった。そうしているうち、女性はどこかへ行ってしまい、一人残された神戸さんは、警報も鳴っていなかったので家まで歩いて戻ったという。出来事を母に話すと「(敵を褒めるなんて)そんなことを外で言ってはいけません」と強く言い聞かせられた。
投下される前日も、いつも通り友人と遊んでいた。日が暮れると、綺麗な夕焼けを見ながら仲良しの「ふみちゃん」と『夕焼け小焼け』を歌いながら帰宅。最後はいつも通り「さよなら、また明日」とあいさつした。次の日、赤紫色の閃光が走った。核爆弾が発した光。その後、ふみちゃんとは会うことができなくなった。彼女の名前は半世紀たってから「原爆供養塔納骨名簿」で見つかった。
被爆者であることを隠して生きてきた神戸さんが語り部を始めて10年。B29やふみちゃんの話を公演会で伝えている。「体験していない人が増えてきた今だからこそ、語らなければいけない」と、戦争の悲惨さを公演会などで伝える一方、親が被爆者の「2世」らを育てる会を発足しようとも取り組んでいる。
近藤さん、吉田さん
旧南多摩郡鶴川村(現野津田町)に住む近藤敏江さん(94歳・終戦当時15歳)と、吉田尚代さん(85歳・同6歳)の姉妹にも記憶をたどってもらった。
近所の野津田には飛行機が落ちてきたという。あまりの轟音に飛び上がり、手に持っていたものを落としてしまった。現場を見に行った時には、道の桜がほころんでいた記憶がある。飛散した破片を探しに隣町まで行った。数年前まで、この時期になると近隣住民らが線香を焚くなど弔いが行われていたという。
赤い東京
東京大空襲の様子は、鶴川村からも見えた。「東京の方面が真っ赤になっていて、『あんなに燃えているんじゃすごいことだろう』という感覚が幼いながらにあった」と吉田さん。都心部へ行ったことが無かったものの、周囲の大人たちが「あっちが東京だ」と騒いでいる姿を見て、緊迫した状況を肌で感じた。あの真っ赤な街の景色は、今でも脳裏に焼き付いている。
終戦から復興
「難しい言葉だったので理解できなかったけど、大人がみんな手を合わせて泣いていた」。二人は敗戦を告げる玉音放送を聞いていた。終戦と同時に生活がガラリと変わることはなかったが、空襲警報に怯える必要がなくなり、安心した記憶もある。
もちろん、苦労の日々はそれからも続いた。様々な物資が不足する生活を、長女として家を支えていた近藤さんは「学校どころではなかった。親を手伝わなくては食べることもできなかったのよ」と回想する。
同地域には親戚のツテを頼って疎開してきた人も多かったといい、小学校の授業は午前と午後の部に分かれた『2部制』になっていたと振り返る。校舎は無事だったが、屋外で授業をしていた。「人数が増えたからかもしれない」。勉強しようにも鉛筆もノートもなかったため、石板にチョークのようなもので書いていた。「自分のものが貰えた時はすごく嬉しかった」と吉田さん。
終戦から復興――。近藤さん、吉田さんら家族だけでなく、多くの人が団結して苦労の時代を乗り越えてきた。「自分一人では歩いていけない。人を思いやる気持ちを大切にしてほしい。今でも誰かの助けを待っている人がいることに気が付いて」。今の時代の人に伝えたい事という。

「今でも固い絆で結ばれています」と家族愛を語る吉田さん、近藤さん、姪の村野千登勢さん(左から順に)
|
|
|
<PR>
町田版のトップニュース最新6件
|
|
|
|
|
|
|
|
|