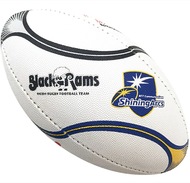「ちょっと待っていて下さいよ。いま昔の資料を引っ張り出すから」。そう言って、棚から一抱えもある文献やファイルを取り出し、鈴鹿明神社や例大祭の歴史をひも解いていく――。神社のすぐ近くに家を構える吉川正昭さん(74歳)は、地域の「生き字引」とも言える存在。例大祭の歴史や思い出を語ってもらった。
言い伝えによると、同神社は531年に創祀(そうし)された。現在の本神輿(1997年完成)の前の神輿は、約310年の歴史があるとされる。例大祭は、1875年までは6月7日から8日間行われていた。1876年に8月1日から6日までに変わり、1928年に今と同じ日程になった。
昔は、皆原・鈴鹿長宿・星の谷の3地区から選ばれた代表者18人が本神輿を担いでいた。「神輿を担いで初めて一人前」と言われていたそう。当時の本神輿は、縦と横にそれぞれ2本の棒が付いていた。中央の「はこ」(=基台)を基点に、担ぎ手たちが棒が地面に付くまでしゃがみこみ、波がうねるように本神輿をゆらしていたという。「担ぎ手の動きに合わせて提灯が揺れてね。すごい綺麗でしたよ」と当時を懐かしむ。
また、文献によると、神輿の胴に巻いたサラシは、渡御(とぎょ)が終わり神社に御霊が移されると、神印が押され、安産のお守りとして産婦に配られていたという。
吉川さんは、市役所や図書館に所蔵されている文献や古文書、家で代々受け継がれてきた資料をもとに地域の歴史を調べている。「今後は調べた内容をまとめようと思っています」。長年の調査で得た、貴重な情報を後世に伝えていく考えだ。

本神輿を差し上げて鳥居まで渡御する担ぎ手
|
座間版のローカルニュース最新6件
|
|
|
|
|
|
|
|
|