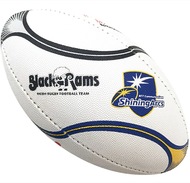その日、広島は風もなく、夏らしくもおだやかな朝を迎えた。忘れることのできない、71年前の8月6日。
沈黙を破ったのは午前8時の空襲警報だった。住民はわれ先にと防空壕に逃げ込んだが、上空を旋回したB―29は何もせずにどこかへと飛んで行った。
警報の解除を受けた人々が普段通りの生活に戻ったその時。2機のB-29が、広島市の上空にやってきたのだった。「また、すぐどこかに行くだろう」。人々は、そのまま逃げることはなかった。
8時15分。数千個のマグネシウムに火が付いたかのような閃光が街全体を包み込んだ。その4千度を超えるとされる熱線はすべてを焼きつくし、新幹線の5倍にあたる秒速400mの爆風が焼跡を吹き飛ばすかのように走り抜けた――。
当時の様子を今に語り継ぐ「座間市原爆被災者の会 ひまわり会」会長、田村良夫さん(74/緑ケ丘)。被爆当時3歳だった田村さんは爆心地から6Km離れた黄金山のふもとに住んでいた。山を挟んでいたことが幸いし、爆風によるケガやヤケドは負わずに済んだという。
「私が記憶しているのは、さっきまで広がっていた青空を覆ったきのこ雲と、のちに爆心地方面から逃げおおせ、幽霊のようによろよろと彷徨う人やうずくまるケガ人たちの姿でした」
多くの人が水を求め、突然に空から降った雨を「恵みの雨」とばかりに手にすくって飲んでいた。そこにたっぷりの放射能が含まれているとは、まだ知る由もなかった。
爆心地方面に住む親せきを心配した田村さんの母は、田村さんを安全な場所に避難させた上で救助に出かけた。そこで大量の放射能を浴び、被爆から10年後に酷い原爆症に見舞われた。毎年夏になると、のどが渇いて仕方ないようで、氷をカリカリと食べていた。「内部被ばくを受けると、内臓や血液が侵される。だるさと無気力が出るから、『原爆ブラブラ病』などと言って怠け者扱いされることも多かった」
被ばく者差別も酷く、「放射能はうつる」「奇形の子が生まれる」などという風評被害が被爆者をより一層苦しめた。終戦後の暮らしも酷いもので、トタンで雨露は凌げても食べ物だけはどうにもならず、雑草や虫で命を繋ぐ日々が続いた。
終戦から71年。「これだけの間、平和が続いたことは奇跡」と語気を強める。「戦争をはじめるのは簡単。でも終わらせる事は、本当に難しい。国全体が暴走し、誰にも止められなくなるから」。平和は当たり前ではない。生き証人が1人また1人と減る中、その一言を伝えるために動き続けている。

講演には欠かさず持参するという被爆者手帳
|
座間版のローカルニュース最新6件
|
|
|
|
|
|
|
|
|