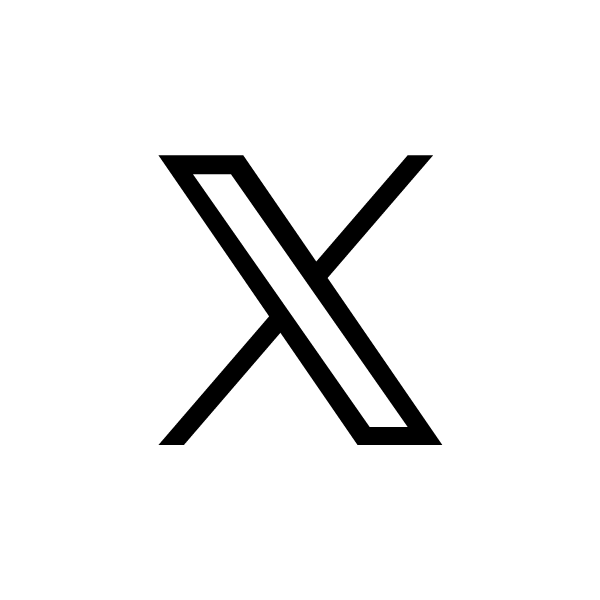2020年の東京五輪開会式まであと1年を切った。聖火ランナー募集も、先月から始まっている。今から遡ること55年前-―。1964年の東京五輪、聖火リレー最終日にランナーを務めたのが後藤和夫さん(73歳・衣笠町在住)。最終走者へ引き継ぐ7人のうち、第2区約800mを激走。日本で初めての五輪に沸き立った当時の様子、その後の”陸上人生”を振り返ってもらった。
インターハイ800mで3位の実力
前回の東京五輪聖火リレーは、9月上旬から約1カ月かけて全都道府県を回り、4コースを繋いだ。陸上総距離6755Km、走者は10万人超と記録されている。都庁に集められた各コースの聖火は「集火式」ののち、開会式当日の午後、皇居前から国立競技場へ男性5人・女性2人によってリレーされた。
その一人が後藤さんだ。横須賀高校の陸上部3年、インターハイで総合優勝を果たしたメンバーで、個人では800m3位を記録した。「最終日のランナーに」と正式な報せが届いたのは、大会が終わって数日後の8月13日。「東京近郊の高校生」を各県の陸連が推薦する形だったという。「実は、最終走者という報道もあったんです」。日本で開催する初めての五輪で報道もヒートアップ。各社の取材が舞い込み、一躍「時の人」に。自宅前には放送局の中継車が待機し、週刊誌でも特集された。当時の記事にはランナーたちを評し、ずらりと並んだメンバーの写真と共に-慎重に選ばれただけに、美しいからだ、力強いフォームの持ち主ばかり。厳粛な祭典の巻頭をかざる大役を果たすにふさわしい人たち-と記されている。
トーチの重みと「重責」
「当日のことは、いまでも鮮明に覚えています」。何回か現地で練習し、周囲からは「格好よく走れよ」との激励の声。そして10月10日、自分に与えられた区間は桜田門から三宅坂までの第2区。「親戚や大津の女子高生の顔も見えた。白バイの後に続いて、お堀端を気持ち良く走れた」と回想する。トーチの重さは約1・3kg。持ち手が下がらないように掲げながら走る――。第3走者に渡り、文字通り「肩の荷が下りた」というのが率直な感想。その後、聖火台に灯す最終走者を務めたのは、広島に原爆が投下された日に生まれた坂井義則さん(早稲田大)だった。
運動と無縁の少年時代
小学校入学前、左足に骨髄炎を患い、「しばらく運動とは無縁の生活だった」。池上中では卓球部に所属していたが、同級生に誘われて陸上部へ。最初は投てきで、トラック競技へ転向。「体育の成績もそれほど良くなく、なかずとばず」だったが、横須賀高校へ進学後も陸上を続けた。そこで出会ったのが、本間慎司先生。「日本一になる」という意気込みに押されるように、1・2年で自身の記録もぐんと伸びた。3年の関東大会800mで優勝、高校最後の大会(インターハイ)を経て、手にしたのが聖火ランナーの大役だった。
「大学では文武両道を目指す」。陸上強豪校からの誘いもあったが、高校2年生の頃に抱いた「南米大陸で仕事をしてみたい」という夢を叶えるため、大学ではスペイン語を学んだ。陸上の大会と授業を”はしご”しながら、記録を残した。就職した東京海上火災保険では、社会人チームに所属。日本選手権でも上位に入賞し、ミュンヘン五輪への出場を目標に掲げて、残業後、皇居前広場などを練習場に月700Km近く走り詰めることもあったという。だが、古傷もあり「トップを目指すという目標に対しては、やりきった」と一線を退いた。
「伴走」の新たな世界
多少のペースダウンをしながらも、赴任先のブラジルでは日系人の大会などに出場。帰国後、誘われたのがブラインドマラソンの伴走だ。「一緒に走る」だけではない。周囲の様子を伝えながら走路やペースに気を配る。「安心して気持ちよく走ってもらう。それに自分が貢献できるのであれば」と、かれこれ20年以上。併走者を長く続けるためにも、日々のランニングは欠かさない。荒天でない限り、ほぼ毎日。佐原や久里浜のほか、母校のグラウンドまで足を伸ばして現役生に声を掛けることも。「3年間地道に練習し、少しずつ力をつけている生徒を見ていると、自分の励みにもなる」。気付けば毎月100Km近く。「走ることがライフワーク。身体の調子を整える感じ」と語る。大きなケガや病気もほとんどなく、今は、陸上に加えて畑仕事やゴルフ、絵を描くことなど多趣味で多忙な日々を過ごしている。
***
もし、聖火ランナーを務めていなかったら―?取材の最後に、そんな質問を投げかけた。「自分は、『走ること』を続けていたと思う。やっぱり陸上と”伴走”する人生を歩んでいたんじゃないかな」―そう語り、日課のランニングに出向いて行った。

最終日走者として桜田門から三宅坂までの第2区を担当(本人提供)
|
横須賀・三浦版のローカルニュース最新6件
|
|
|
|
|
|
|
|
|