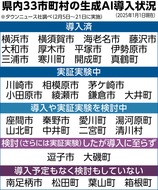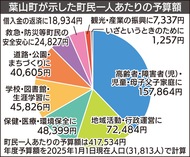海藻を食いつくし、磯焼けの原因になっているムラサキウニ。逗子海岸でもその数が増えており、漁業関係者らが頭を悩ませている。対策を講じようと海と山が近い逗子葉山ならではの資源循環を作るプロジェクトが始動。市民も巻き込んで逗子の海を豊かさを取り戻し、持続可能なモデルを作ろうと意気込む。
今月15日、逗子マリン連盟と逗子30,Sの共催で「磯焼け対策 逗子ウニひろい」が開催され、市民やマリンスポーツ事業者、漁業関係者ら約100人が参加した。海水温の上昇やアイゴ、ムラサキウニなどによる食害でカジメやワカメといった海藻類が減り、海底が砂漠のようになる「磯焼け」。逗子海岸でもその被害は深刻で、小坪漁業協同組合の大竹清司組合長によると「年を経るごとに沿岸の海藻がなくなり、西浜や浪子の磯場にかけては、ウニがびっしりと生息している」という。失われた藻場は海の「生命の揺りかご」とも言われ、魚介類の生育に欠かせない環境。各地で様々な試みが行われているが、抜本的な解決策は見つかっていない。
逗子市では、地元選出の近藤大輔県議が協力。県やマリンスポーツ関係者、漁組、そして葉山の農家をつなげ、海の厄介者であるウニを資源として循環させる仕組みを構築した。
今回捕獲したウニは葉山石井ファーム(上山口)が引き取り、農業利用するためにたい肥化。有機物をたっぷり含んだ肥料で、葉山野菜の栽培に使うという。また、県水産技術センターの協力を得て、生態系の経年変化を観察。「ウニひろい」の効果測定や対策の効果的な手法を探る。
当日は、親子連れも参加。西浜からすぐの岩場に多数のウニがいるのを見つけると、子どもたちは「こんなにいるよ」と器用にトングを使って捕獲していた。逗子マリン連盟の小林太樹さんは「今後も開催していくので、市民の皆さんと一緒に逗子の海の豊かさを取り戻せたら」と話していた。最新情報は同団体フェイスブックページで発表される。
また、今回の事業は漁業組合等の許可を得て行っているもので、一般市民が普段、ウニを捕獲すると法律により罰せられる。
逗子・葉山版のトップニュース最新6件
|
|
|
|
|
|
|
|
|