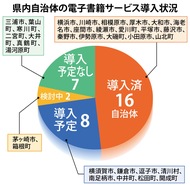寒川町の目久尻川で新種の水中植物が発見され、外来種の『コウガイセキショウモ』だということがわかった。寒川町の自然環境保護に尽力している渡辺充さんが発見し、現在、駆除を行っている。
渡辺さんは昨年7月、それまでに見たことのない沈水植物を発見。標本を生物調査会社に見せて相談したところ『セキショウモ』ではないかといわれた。しかし、相模川水系では絶滅し姿を消しているという認識があり、開花を待って再び標本化し、相模原市博物館の門をたたいた。
そこでは学芸員の秋山幸也さんが対応してくれ、既存の『セキショウモ』属の特徴には一致しないことが判明。秋山さんの慎重な判断により、水生植物を専門とする日本大学応用生物科学科、植物細胞学研究室の内山寛教授を紹介された。
今年4月、内山教授の研究室に標本を持ち込むと、2016年に報告された新種の外来種『コウガイセキショウモ』であることがわかった。
相模川水系では初
内山教授によると『コウガイセキショウモ』は多摩川・鶴見川水系にみられ、相模川水系では初めて。酒匂川水系ではみられなくなったという。強い繁殖力により他の生物を駆逐する危険性が高く、『セキショウモ』に限らず在来生物の生態系に影響を与える可能性を指摘している。
特定外来種には指定されていないが、環境省の生態系被害防止外来種(重点対策外来種)に指定。在来の『セキショウモ』は県内では芦ノ湖と川崎市多摩区の一部に残っているだけで、県のレッドデータブックで絶滅危惧IA類とされている。標本は文化財学習センターと相模原市博物館に保管してある。
渡辺さんは寒川町に住んでいたことがあり、当時から自然環境の保護に努めていた。勤務先の関係で引っ越した今でも、主に目久尻川で生態系被害防除のためアライグマの駆除に尽力しており、その過程での発見だった。『コウガイセキショウモ』の駆除は9月から始めたが、台風による増水などで難航しており、完全駆除には至っていない。
識別難しい
また、絶滅危惧種の在来種との識別は非常に難しく「似た水草があったとしても安易に抜かないで下さい」と同博物館の秋山さんは呼び掛けている。

駆除された「コウガイセキショウモ」と標本(右下)
|
寒川版のトップニュース最新6件
|
|
|
|
|
|
|
|
|